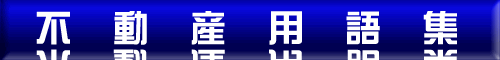成年被後見人 【せいねんひこうけんにん】 |
精神上の障害があるために、後見人を付けられた者のこと。
精神上の障害により物事を判断する能力が欠如した状態にある者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求に基づいて審判を行ない、「後見開始」の決定をし、「後見人」を職権で選任する(民法第7条、第843条)。
こうした手続により後見人を付けられた者のことを「成年被後見人」と呼ぶ。
また、成年被後見人に付けられる後見人は「成年後見人」と呼ばれる。
この「成年被後見人」の制度は、平成12年の民法改正によって創設されたもので、それ以前は「禁治産者」という名称であった。
成年被後見人は法律行為を有効に行なうことができないものとされているので、どんな法律行為でも原則的に後で取消すことが可能である(ただし日用品の購入などは有効に自分で行なうことができる)(民法第9条)。
従って、成年被後見人との契約を行なうには、その成年後見人を代理人として契約を行なうべきである(民法第859条)。 |
石綿 【せきめん】 |
蛇紋石・角閃石など繊維状ケイ酸塩鉱物の総称。繊維質であるため紡績することができる。
引張強さが大きく、また溶融点が1,300℃程度と高く、熱絶縁性が大きいため、保温材、断熱材として利用される。また、セメントや石灰、珪藻土などと混合して断熱・保温のために吹き付けたりする。しかし、石綿の粉塵が人体に健康障害を及ぼすことが社会問題化し、大部分のアスベスト製品が代替化やノンアスベスト化されている。 |
石灰石 【せっかいせき】 |
炭酸カルシウム(CaCO3 )を主成分とする天然鉱石のこと。
石灰は英語で「lime」(ライム)という。 |
設計住宅性能評価書 【せっけいじゅうたくせいのうひょうかしょ】 |
登録住宅性能評価機関が設計図等に基づいて作成した住宅性能評価書を「設計住宅性能評価書」という(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同法施行規則第3条)。
住宅品質確保法では、設計住宅性能評価書を交付された新築住宅については、設計住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定しており、この規定により注文者保護・買い主保護が図られている。(詳しくは「住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係」へ)
このような設計住宅性能評価書が作成される手順はおよそ次のとおりである。
1)作成の依頼
新築住宅の請負人または注文者(もしくは新築住宅を売却する売り主または買い主)が、登録住宅性能評価機関に対して、設計住宅性能評価書の作成を依頼する(同法施行規則第3条)。
この評価書作成の費用は10万円から30万円程度といわれているが、その費用は請負人または注文者(もしくは売り主または買い主)が負担することになる。
なお既存住宅(建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある住宅のこと)については、設計住宅性能評価書の作成を依頼することができない。
2)必要な書類の提出
依頼者は、登録住宅性能評価機関に対して、設計住宅性能評価書を作成するために必要な関係書類を提出する。
この依頼者が提出すべき書類は、配置図・仕様書・各階平面図など非常に多岐にわたる(提出書類は国土交通省告示「設計住宅性能評価のために必要な図書を定める件」により定められている)。
3)設計住宅性能評価書の作成
登録住宅性能評価機関は提出された多数の書類に基づき、国土交通大臣が定めた基準に準拠して、新築住宅の性能を評価し、設計住宅性能評価書を作成する(このとき評価する項目の詳細は「日本住宅性能表示基準」へ)。
このように設計住宅性能評価書は、あくまで設計図等の書面のみに基づく評価結果であり、現地で住宅を検査した結果に基づく評価ではない。
そのため、請負人・注文者(もしくは売り主・買い主)が、検査結果に基づく住宅性能評価書の作成を希望する場合には、登録住宅性能評価機関に対して建設住宅性能評価書の作成を別途依頼する必要がある(同法施行規則第5条)。
このようにして依頼者の費用負担で作成された設計住宅性能評価書を、実際に請負契約書・売買契約書に添付等するかどうかは請負人・売主の自由に委ねられている(同法第6条)。
なお、設計住宅性能評価書が交付された住宅については、弁護士会に対して原則として1万円の費用負担で紛争処理を申請することができる(同法第62条、同法施行規則第104条・第105条)。
しかし設計住宅性能評価書だけが交付されている住宅については、この紛争処理の申請をすることができない。(詳しくは「指定住宅紛争処理機関」へ) |
設計図書 【せっけいとしょ】 |
建物を施工するために必要な図面その他の書類の総称。建築士法では建築物や工作物だけでなく敷地を含めた工事実施のために必要な図面と仕様書、と規定されている。
実際には、施工段階で設計変更、仕様変更、追加工事等が生じることが多いために、竣工図という最新の設計内容を記録した設計図書がある。これらは、経年に伴う改修・改築等の際に必要なものであるため、建築主は必ず保管しておく必要がある。 |
石膏 【せっこう】 |
硫酸カルシウム(CaSO4)を主成分とする物質のこと。
二水石膏(CaSO4・2H20)、半水石膏(CaSO4・1/2H20)、無水石膏(CaSO4)の3種類がある。
二水石膏を焼成すると半水石膏となる。このため半水石膏を「焼石膏」ともいう。
この焼石膏に水を加えて練ると、流動性の液体となるが、この液体は数分から数十分で再び二水石膏となり固体化する。
このような性質があるため、石膏は左官材料等として多用されてきた。
また石膏には、天然に産出する天然石膏と人工的に生産する化学石膏とがあるが、わが国で用いられる石膏の大半は化学石膏である。
石膏は英語で「gypsum」という。 |
石膏プラスター 【せっこうぷらすたー】 |
石膏(焼石膏)に水、砂などを混ぜ合わせたものを「石膏プラスター」という。左官材料などに用いる。
また、石膏(焼石膏)、消石灰、水、砂などを混ぜ合わせたものは「混合石膏プラスター」という。
|
石膏ボード 【せっこうぼーど】 |
石膏を心材とし、両面をボード用原紙で被覆した板のこと。
施工が簡単で、温度・湿度による変化が非常に少ないことから、壁材、天井材(あるいは壁・天井の下地材)として多用されている。 |
絶対高さの制限 【ぜったいたかさのせいげん】 |
第1種・第2種低層住居専用地域では、住環境をよくするために、建築物の高さが10メートルまたは12メートル以下に制限されている。これを「絶対高さの制限」と呼んでいる(建築基準法55条)。
この絶対高さの制限が「10メートル以下」と「12メートル以下」とのどちらになるかは、都市計画で規定される。
なおこの絶対高さの制限には例外がある。建築審査会が同意して特定行政庁が許可した場合には、絶対高さの制限を上回る高さの建築物を建築することができる。 |
接道義務 【せつどうぎむ】 |
都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている(建基法43条)。
|