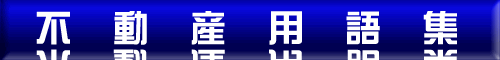使用貸借 【しようたいしゃく】 |
動産や不動産を有償で貸し付ける契約が「賃貸借契約」であるが、無償で貸し付ける契約は「使用貸借契約」と呼ばれる。
使用貸借契約については、借地借家法が適用されず、民法第593条から第600条が適用される。また無償で貸し付けているため、使用貸借契約においては、貸し主は原則としていつでも借り主に対して契約を解除し、物の返還を要求することができる(ただし存続期間を定めている時はその期間が満了するまでは物の返還を要求できない)(民法第597条)。
実際には使用貸借契約は、会社とその経営者の間で締結されたり、親子間で締結されることが多い。また契約書が存在せず、口約束で行なわれることも多い。
例えば会社の経営者が、個人名義の土地の上に会社名義の建物を建築するケースや、親名義の土地の上に子名義の建物を建築するケースなどである。
なお税法上の相続財産評価においては、使用貸借契約により土地を貸借する権利の経済的価値はゼロと評価されている。 |
上棟 【じょうとう】 |
棟上げ
棟木を納めること、もしくはその時に行なう儀式のこと。
新築への祝福と神の守護に感謝を示し、同時に無事建設されることを祈願する。建築工事の着工と完了の中間にあり、建物の形態がおおよそ整った時点を指す。 |
譲渡担保 【じょうとたんぽ】 |
債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。
債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。
|
譲渡担保 【じょうとたんぽ】 |
債務者(または物上保証人)の所有する物(動産でも不動産でもよい)を、債務者(または物上保証人)が債権者に譲渡し、債務を全額弁済すると同時に債務者(または物上保証人)が債権者からその物を買い戻すという制度である。
担保に入っている期間中は、債権者(すなわち物の所有者)が、その物を債務者に賃貸するという点に最大の特徴がある。この意味で譲渡担保とは、買戻または再売買の予約に、賃貸借を組み合わせた制度であると言うことができる。
譲渡担保においては債務が弁済されない時は、債権者(すなわち物の所有者)はその物を確定的に所有できることとなる。その場合、債務の金額を物の価額が超える場合には、債権者はその超過部分を債務者に返還する必要があり、この債権者の義務を清算義務という。清算義務は判例により確立したものである(昭和46年3月25日最高裁判決など)。 |
消費税 【しょうひぜい】 |
国内の資産・商品・サービスの取引によって発生する付加価値に対して課税される税金。
法人や個人事業者が有償で行なう「資産の譲渡」「商品の販売」「資産の貸付け」「サービスの提供」は原則としてすべて消費税の課税される「課税取引」とされている。
また土地の販売・住宅の家賃のように、税の性格や社会政策的配慮により消費税が課税されないこととされている取引は「非課税取引」と呼ばれる。
なお課税取引にもとづく売上高が一定規模に達しない法人や個人事業者については「免税業者」や「簡易課税制度」という措置が設けられている。 |
消滅時効 【しょうめつじこう】 |
一定期間、権利を行使しないという事実状態が継続することにより、債権などの権利が消滅するという時効を消滅時効という。消滅時効にかかる権利は債権、用益物権、担保物件であるが、権利の性質により消滅時効が完成するまでの期間はさまざまである。
普通の金銭債権は10年間行使しないことにより消滅時効によって消滅する(民法第167条第1項)。また用益物権は20年行使しないことにより消滅する(民法第167条第2項)。
またその性質により短期で消滅させるべき債権は5年、3年、2年、1年の短期消滅時効により消滅する(民法第168条から174条)。 |
証約手付 【しょうやくてつけ】 |
手付の一種で、売買契約などが成立したことを証するために交付される手付のこと。
売買契約などが締結されるまでにはいろいろな交渉段階があり、どの時点で契約が成立したのかが一見明確でないことが考えられるので、そのような場合において契約の成立を証明するために交付される手付のことを証約手付けという。
ただしわが国では、手付とは原則として解約手付とされている。
|
植栽 【しょくさい】 |
敷地内の花壇や空いているスペースに樹木や草花を植えること。視覚的に生活を豊かにするだけではなく、災害時の避難場所、気候調節等、さまざまな効果・役割がある。 |
職務行為 【しょくむこうい】 |
法人の理事が、法人の目的の範囲内で行なう行為のこと。
法人は定款または寄附行為に定められた目的の範囲内で、権利を取得し、義務を負担することとされているので、法人の代表機関である理事はこの目的の範囲内で代表機関としての行為を行なうことができる。このような理事の行為のことを一般に「職務行為」と呼んでいる。(法人の権利能力・行為能力を参照のこと)
理事の職務行為が問題となるのは、法人が不法に他人に損害を与えた場合(=法人に不法行為責任が発生する場合)である。
民法第44条第1項では「理事などの代表機関が職務を行なうにつき他人に加えたる損害は法人が賠償する責任を負う」と規定して、法人が不法行為責任を負うことを明記している(詳しくは法人の不法行為責任へ)。
しかし、仮に上記の「職務を行なうにつき」という言葉を厳格に解釈するならば、そもそも理事が不法に他人に損害を与える行為自体が「職務」の範囲から除外されるという問題が生じる。
〔不法に他人に損害を与える行為はもはや法人の代表機関としての行為には該当しない、と考えることができる〕
しかし、それでは法人の不法行為責任が発生するケースは存在しないことになってしまい、法人の不法行為責任を規定した民法第44条第1項が無意味なものとなる。
そこで判例では、「職務を行なうにつき」という言葉を次のように広く解釈している。
1)外形上「職務行為」と見える行為は、「職務を行なうにつき」に含める。
2)社会通念上「職務行為に関連する行為」は「職務を行なうにつき」に含める。
このように「職務を行なうにつき」という言葉を広く解釈することにより、法人の不法行為責任が成立する範囲を拡大し、法人の不法行為による被害者を救済しているのである。
なお、職務行為という言葉は、上記の1)と2)をあわせた意味で使用されることがある。本来職務行為とは、上述のように法人の代表機関の正当な行為のことを指すのであるが、法人の不法行為責任を論じる場合には、民法第44条第1項が適用されるすべての行為(上記1)と上記2))を「職務行為」と呼ぶことが多いので、注意したい。 |
所得控除 【しょとくこうじょ】 |
所得税の計算において、所得から差し引くことができるさまざまな控除のこと。
所得控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除などがある。
給与所得者の場合には次の計算によって課税総所得金額が計算される。
「給与収入 − 給与所得控除 − 所得控除 = 課税総所得金額」
この課税総所得金額に所得税率を掛けることにより、所得税額が算出される。 |