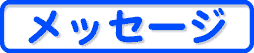|
皆さんにおかれましては、頭痛の種の確定申告もやっと終わり、春の訪れとともに気分が明るくなってきた今日この頃ではないでしょうか。
巷では戦争等、相変わらず暗い話題が多いようですが、新年度とともに気分を一新したいものですね。
最近の日本の動向を見ていますと、段々とUSA(アメリカ)的になってきているような気がします。
以前より日本はUSAを数年遅れで追いかけているといわれておりましたが、社会、経済のトレンドを見てみると正にいまだにこの法則は当てはまっているようです。
社会面では、日本における凶悪犯罪が急増しています。日本は、世界の中で最も安全な国といわれておりましたが、現在では正しくはありません。とくに東京などの都市部での犯罪は、段々と凶悪化しており、USAの都市部、ニューヨーク・ロスアンジェルス・デトロイト等と近いレベルになってきたような気がします。
私が十数年前、ニューヨークのマンハッタンで生活していた頃、アッパー・イーストのいわゆる高級住宅街でも塩酸を通行人にいきなりかけたり、鉄棒でいきなり殴り殺したりというような犯罪が大きく取り上げられていたほど荒廃していました。昨今の東京でのニュースを聞いているとその頃を思い出してしまいます。世田谷や成城あたりのいわゆる高級住宅街でも殺人や傷害事件が多発しています。路上生活者を少年が殺すというような事件にもさほど驚かなくなりました。それほど、日本の安全神話は崩壊しているということです。
私の働いている会社はUSAに本社がありますが、アジア極東地域を担当することになったアメリカ人Executiveが家族をつれて日本に来ることに安全性の問題で躊躇するケースも出てきてます。言葉の問題もあり、日本ではなくシンガポールに住むことを希望する外国人が増加しているようです。
また、経済面では、日本でも「持つ者」と「持たざる者」の二極化が明確になってきました。USAでは数%の富裕層とその他という区分が明確になっていますが、日本も段々とその傾向にあるようです。
10年前まで「一億総中流」等といわれておりましたが、今ではこの言葉は全く聞かれなくなりました。
私に言わせるとまだまだ甘いですが、日本のサラリーマンも段々と能力主義で評価されるようになってきたとメディアでは大きく取上げられるようになってきました。労働組合による春闘一斉値上げ闘争も以前程の力強さもありません。
やっと、日本にも世界の常識が適用されてきたようです。
そもそも「一億総中流」等ということはありえません。また、そうすべくコントロールしようとすると必ず歪みが生じて結果的に破綻することは、当然の成り行きです。
このアパマンニュースの読者の方々は、既に「持つ者」もしくは「持つ者」になろうと努力している方々であるわけですから、周りの人達と同じことを考え実行していたのでは、先が見えています。
あんなばかげた「国債」を「絶対儲かる」等と軽口をたたくようなエセ経済学者の言葉を信じて買っているようでは、お先真暗です。「絶対儲かる」ものが世の中に存在するとしても、メディアで取上げられた時点で価値はゼロです。皆が儲かるなんてことは論理的にあり得ませんし、仮に儲かったとしてもゼロに近い儲けでしょう。
過去に話題になったネズミ講等を振返ってみればお分かりかと思います。
数年前に証券会社が大宣伝をやって募集した株式投信ファンドに投資した方も多くいらっしゃると思いますが、あれは「みんなで買えば恐くない」の典型でした。日本人の特質をうまくとらえた最高のマーケット戦略だったと思います。証券会社は確かに莫大な手数料を濡れ手に泡で稼ぎ出し、担当者は多額のボーナスを得ました。そのつけは、今では全て「右に習え」で深く考えずに投信を買った人々に転化されています。
既にお読みになった方も多くいらっしゃるかもしれませんが、本を一冊ご紹介したいと思います。
最近のベストセラー「お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方(知的人生設計入門)」橘玲 著 です。
この本の中では、今後の自分および家族の人生を設計していく上でのいくつかのヒントが示されています。
私は、以前よりこの橘玲氏の著作が好きでした。私と同年代でもあり、考え方も私とベクトルが合っています。本書の中では、国家・税金との付き合い方、サラリーマンと法人の制度上の違い等がわかりやすく述べられています。この中で、不動産に関する部分に関しては、私と見方が一部異なっていますが、非常に有益な情報を公開していますので、ぜひ御一読をお勧めします。
この中で説明されている「永遠の旅行者」(Perpetual Traveler)を私は目指しています。
理不尽な使い方を余儀なくされている税金や年金をいかにして搾取されずに生きていくかというのは今後、益々重要になってくると思います。
本書の中で示されている
資産形成=(収入−支出)+(資産X運用利回り)
という単純な方程式には、今後どのようなアクションをとるべきかが全て含まれています。
特に支出の多くを占める税金との付き合い方が重要になるのではないでしょうか。
|
|